

こんな疑問にこたえます。
これを書いている人(さあや)はかれこれ10年以上ラテン語に取り組んでいますが、はじめの頃は難解な文法にとまどっていました。そんな経験をふまえて書いていきます。
この記事でわかること
・ラテン語が難しい理由
・レベル別の対策:初級、中級、上級編
目次
ラテン語は難しい
ラテン語は約2000年前の古代ローマで話されていた言葉です。長い歴史を経て現代にも足跡を残しているため、さまざまな理由で今でも勉強されています。難しいとよく言われていて、実際に学習してきた私も難しいと思います。その理由はこちらです。
なぜラテン語は難しいのか
そもそも文法が難しい
ラテン語は何よりもまず、文法が難しいです。たとえば、こちら。
| 単数 | 複数 | |
| 主格 | rosa | rosae |
| 呼格 | rosa | rosae |
| 属格 | rosae | rosarum |
| 与格 | rosae | rosis |
| 対格 | rosam | rosas |
| 奪格 | rosa | rosis |
バラを意味するrosa(読み方はロサ)という単語は、文中での機能によってこれだけ変化します。rosaに限らずすべての単語が同じだけ変化しますし、変化の種類も一つではありません。名詞だけでも5種類の変化があります。
『ベルサイユのばら』の作者、池田理代子は音大でのラテン語の勉強についてこう書いています。
同じ土曜日にとっている「イタリア語」の授業がむしろ楽に感じられるくらい、ラテン語は難しく苦しい。
苦しいが、しかし楽しい。はっきりいって、まるでジグソーパズルの世界である。どのように苦しく楽しいかというと、たとえば、
Homo homini lupus. Nos autem in homine hominem videre studebimus.(人間は人間に対して狼である。それでもわれわれは人間の中に人間を見るよう努める)
という文章のように、“人間”を意味するhomoという単語のさまざまな変化形と格闘して、気も違いそうに混乱する濃密な時間を過すのだ。
ああ、たったこれだけの文章を解読するために、何十分という時間が費やされることか!
池田理代子『47歳の音大生日記』
池田理代子氏のおっしゃるように、homoという単語はhomini、homine、hominemと変化します。こんな変化を名詞、形容詞、動詞、代名詞ごとに学んでいくため、ラテン語は難しく大変と感じるのです。
ネイティブがいない
ラテン語は古代ローマで話され、書かれていました。時代を経ると当然のように話し言葉は変わっていきます。しかし、書き言葉としてのラテン語は使われ続けました。現代において、ラテン語は文字においては存在していますが、母語として話す人はいません。
外国語を勉強する時、その言葉のネイティブスピーカーの発音を何らかの形で聞いてマネしたり、機会があればネイティブスピーカーと会話したりするかと思います。
ラテン語ではそれができません。せっかく文法を覚えても、それを使ってネイティブと会話することがないとなれば、勉強は読むことが中心となってしまいます。聴覚、発話面での刺激が比較的少ない、内向きの地味な学習になりがちです。
「わかりやすい」ものがあまりない
ラテン語の学習教材は辞書や文法書を含めて日本でも出版されているものの、種類は限られています。この点で、子供用の初歩から大人向けの上級編までさまざまなレベルの教材が充実している英語とはまったく違います。
音声教材もあり、わかりやすい無料の動画解説を手軽に楽しめ、ネイティブスピーカーとも気軽にオンラインで会話できる英語学習に慣れている人ほど、ラテン語教材の地味っぷりには驚くかもしれません。
難しくないところもある!
とはいえ、ラテン語も難しいところばかりではありません。こちらをご覧ください。ガリア戦記の冒頭です。
Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.
文字は見覚えのあるものでしょ!
ラテン語のアルファベットは英語でもおなじみのものです。ロシア語やアラビア語とは違って、文字から覚える必要はありません。発音も、ほぼローマ字読みなので日本人にとってはらくちんです。上のガリア戦記はこう読みます。
Gallia(ガッリア) est(エストゥ) omnis(オムニア)
divisa(ディーウィーサ) in(イン)partes(パルテース) tres(トレース)
どうです? できそうじゃないですか?
また、動詞はたいてい規則動詞です。フランス語やドイツ語などの現代語は文法書や辞書の後ろに動詞の変化表が載っていて、これを覚えるのが初級を突破する一つの関門だったりします。ラテン語にはこのような単純な暗記はあまりありません。
難しいのは確かですが、とっつきやすい面もあるのです。
また、ラテン語は現代においてフェアな言語と言えます。なぜかというと、全地球上で今現在ラテン語を母語とする人がおらず、みんなにとっての外国語であるからです。英語がペラペラなアメリカやイギリスの方々も等しく、ラテン語を外国語として一から学びます。ネイティブから習えないというデメリットも、こうしてみればメリットにもなります。
学ぶ価値もある
私は10代のころ、「ラテン語は英語の語源」と聞いて興味を持ち、世界史の文化史で知ったローマの書物を原典で読んでみたくて、大学に入学してからラテン語を学び始めました。
他にもラテン語を学ぶ動機は人それぞれいろいろあると思います。こちらの記事もご覧ください。
-

-
【知っておくべき】ラテン語を勉強した方がいい理由【多方面から解説】
ラテン語って今は使われていないのに、どうして勉強するの?ラテン語を学ぶ意義ってなに?どんなメリットがあるの? そんな疑問に答えます。 こんな方におすすめ ラテ ...
続きを見る
この記事を読んでいるあなたも、きっとなんらかの心当たりがあるのではないでしょうか?
ラテン語について知ってみたい方におすすめの本があります。
ラテン語について書かれた日本語の本の中で、いちばん通読しやすく、読んだ後はほんのり温かい気持ちになれる本です。
ラテン語について紹介されたオーソドックスな本です。
日本で手に入る学習教材もご紹介。
こちらの記事もどうぞ。
-
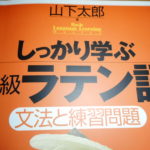
-
【独学ならこれ一択】しっかり学ぶ初級ラテン語【徹底レビュー】
ラテン語学習歴10年以上のさあやがラテン語の教科書『しっかり学ぶ初級ラテン語』のレビューをします! 目次『しっかり学ぶ初級ラテン語』メリットとデメリットメリッ ...
続きを見る
ラテン語の難しさへの対処法
ここからは、すでに学んでいる人のために、ラテン語の難しさへの対処法をレベル別に書いていきます。
全般編:英語学習とは真逆と心得る
まずは全レベルの学習者へのアドバイスです。大事なのは、「英語学習とは真逆と心得る」こと。これまでの英語学習の体験はほぼ通用しないと思いましょう。これは何回も心に刻み、肝に銘じましょう。(ただし、受験英語などで培った綿密な英文解釈は、ラテン語を解釈する際にも活きてきます)
詳しく説明します。
時間のかかる覚悟をする
先に書いたように、ラテン語は難しいです。だから、ラテン語の勉強には時間がかかります。この記事を読んでいるあなただけではなく、みんな同じです。佐藤優もこう言っています。
筆者は、同志社大学神学部に入ってから小説をほとんど読まなくなった。
神学を本格的に勉強するには、ドイツ語、新約聖書ギリシャ語、ラテン語などの面倒な外国語を習得しないとならない。さらに神学は、哲学の言葉を用いて議論することが多いので、哲学史の勉強もしなくてはならない。
それだから、下宿にあったテレビと小説類はすべて友人に贈与し、勉強時間を確保した。
『週刊現代』2016年10月29日号
テレビや小説とキョリを取るかはお任せしますが、時間の確保は大事かと思います。
わからなくても先に進む、完璧を目指さない
難しいので、全てを理解して、完璧にしてから先に進む、という10代の英語学習では通用したかもしれない勉強法はあきらめましょう。たとえわからなくても、もしかしたらさっぱりなことがあったとしても、とりあえず学習を進めましょう。
授業に出ている人は出続けましょう。独学の人は文法書を最後までやってみましょう。一通り目を通してから初めに戻ると、案外理解できてしまうこともあります。
忘れてもOK
復習した際に、前に学習したことを忘れていても、落ち込む必要はありません。また覚えなおせばいいのです。学習法の研究では、思い出そうとすることで記憶に定着することが明らかになっています。忘れていたのだとしたら、むしろ記憶が強化されてラッキーくらいに思っておきましょう。
初級編:つづけること、習慣づくり
ラテン語の勉強を始めてから1年前後の、初級文法を学んでいる人へのアドバイスは、とにかく「つづけること」です。
先に紹介した池田理代子の言うように、ラテン語がジグソーパズルのように感じる段階だと思います。パズルがとけなくて大変! 一語ずつ単語の意味を調べたり、どの変化なのか見当をつけたりと時間がかかることでしょう。私も文法に四苦八苦していた頃、ラテン語はパズルだと思っていました。
ラテン語を学んでいるなら、初級文法を学んでやってみたいことがあるはずです。ラテン語で読んでみたいものがあるとか、新生物を発見してラテン語の学名をつけたいとか。
ラテン語との関わりが文法を勉強した後も続くのだとしたら、文法が難しくて大変だとしても、わからないことがあっても、(全般編でも書いたように)あきらめないでとりあえず続けてみることをおすすめします。
続けるうちに全体像が見えてきて、少し前までわからなかったことが気づいたらわかるようになっていたりと、どんどん理解度は深まっていきます。
週に2回でも3回でも、毎週継続してラテン語を勉強する習慣づくりがこの段階では大切なのです。学習法の研究では、集中的に時間をかけて勉強をする「集中学習」よりも、間隔をあけて勉強をする「分散学習」の方が効果的とされています。この方法にのっとると、週に1日、何時間も勉強をするより、週に2日か3日に分けて勉強をするのがよいことになります。
続けやすいペースを見つけられたらいいですね。何曜日にやるのか、一日のうちいつやるのか、朝なのか、晩なのか、昼休みなのか、などなど見極めながら、生活の中にラテン語学習を組み込んでしまえたらこっちのものです。
もし今現在、どうしても難しくて苦痛だとしたら、こちらのものは確実に覚えるようにしてください。
これだけは覚えよう
・名詞の第一変化と第二変化
・動詞の直説法の活用
これ以外は、丸暗記できていなくても、変化表や活用表を見ながら文法書の例文や練習問題に取り組めれば、まずはよいかと思います。
特に、qu~ではじまる関係代名詞や疑問代名詞、hicなどの指示代名詞の変化を暗記するのは初級文法よりももっと後の段階で十分です。いつの日か、覚えた方が楽かもと悟った時に覚えましょう。
もしこの段階で秘策があるとしたら、格の並べ替えです。こちらをご覧ください。先に紹介したrosaの変化表です。
| 単数 | 複数 | |
| 主格 | rosa | rosae |
| 呼格 | rosa | rosae |
| 属格 | rosae | rosarum |
| 与格 | rosae | rosis |
| 対格 | rosam | rosas |
| 奪格 | rosa | rosis |
これをこう並べ替えたらどうでしょうか?
| 単数 | 複数 | |
| 主格 | rosa | rosae |
| 呼格 | rosa | rosae |
| 対格 | rosam | rosas |
| 属格 | rosae | rosarum |
| 与格 | rosae | rosis |
| 奪格 | rosa | rosis |
同じ形が並んですっきりしますよね。この順だと、やっかいな第三変化lex(法律)の変化(↓)も
| 単数 | 複数 | |
| 主格 | lex | leges |
| 呼格 | lex | leges |
| 属格 | legis | legum |
| 与格 | legi | legibus |
| 対格 | legem | leges |
| 奪格 | lege | llegibus |
こちらのように(↓)同じ形が並んですっきりします。
| 単数 | 複数 | |
| 主格 | lex | leges |
| 呼格 | lex | leges |
| 対格 | legem | leges |
| 属格 | legis | legum |
| 与格 | legi | legibus |
| 奪格 | lege | legibus |
複数の主格、呼格、対格は同じで、複数の与格と奪格も同じ形ですので、この表のように並んでいるととてもわかりやすいのです。
私が初級文法を学ぶ際に使っていた文法書はこちらの順を採用していたので、比較的楽に覚えられたと思います。
こちらの本も、同様の格の並びを採用しています。
何はともかく、とりあえず文法を最後までやってみましょう。大学やカルチャーセンターで文法を学習中の人は、まわりにいる人がとてもできるように見えてしんどいかもしれません。
でも、もしかしたらその人は一度挫折して、2回目の受講中かもしれません。もしかしたら、語学の天才かもしれませんし、家ではめちゃくちゃ頑張って人前では涼しい顔をしている人かもしれません。
そんな人のことは気にせず、自分自身が1ミリでも成長していくことを望みながら、初心を忘れずに、ラテン語をのびのび続けてみましょう。
中級編:音読する、ストックを増やす
初級文法を勉強し終わってから、まとまった量の文を読んでいる段階をここでは中級とします。
まず戸惑うのは、英語などとは違って、長文の文法事項を解説したような「英文解釈」のような本や、カリスマ予備校講師による心底わかりやすい授業がオフラインでもオンラインでも、あまりないことではないでしょうか。
ないものは仕方ないので、これまでの受験英語や英文解釈を思い出して、ラテン語の解釈もがんばってみましょう。
単語を一つずつ、辞書で引くことになるでしょう。文法や名詞の変化、動詞の活用も文法書に立ち返って確認することになるでしょう。そんなことを繰り返しながら、文を見てパッと「あの文法事項!」と思いだせるようになるくらい、初級文法が生きた知識となるのを目指しましょう。
1文を読むのにも、何度も辞書を引くため、予想もしないほどの時間がかかることもあるかと思います。
須賀敦子はこう言っています。
学生のころ、古典だからという理由だけのために、まるで薬でも飲むようにして翻訳で読み、感動もなにもなかったウェルギリウスの叙事詩『アエネイス』を、ほとんど一語一語、辞書をひきながらではあってもラテン語で読めるようになって、たとえば、この詩人しか使わないといわれる形容詞や副詞や修辞法が、一行をすっくと立ち上がらせているのを理解したときの感動は、ぜったいに忘れられない。
須賀敦子「塩一トンの読書」
きっと、時間をかけて読んでいった先では、このような感動を味わうことになると思います。なんとも良い経験ではないでしょうか。
この段階で大切なのは、丁寧に解釈したことを着実に身につけていくことです。ラテン語といえど、よく出る構文というものがあるため、一つずつ焦らずに身につけて脳内にストックを増やしていくと、次に似たような文が出てきたときに、きっと楽に読むことができます。
そのためには、何日か空けて忘れた頃に復習して、文の意味を確かめることです。慣れるためには、音読するのもいいでしょう。英語学習で音読した経験のある人は、それと同じ感覚でやってみましょう。
私はこの段階で復習をおろそかにしたために、予習に時間はかけているものの、なかなか身についている実感を得られず、しばらく暗い時期を過ごしました。これを読んでいる方は、そうならないように、予習→授業→復習のサイクルを作りましょう。独学の方も、先に先にと進むだけでなく、時には復習の時間も取りましょう。
この習慣を続けるうちに、パズルのように思えていたラテン語が、しだいに語のまとまりごとに把握できるようになるでしょう。
もし、あまりにも予習に時間がかかるなら、単語をある程度覚えてしまうのをおすすめします。初級文法書に出てきた単語をいったん覚えてしまうと、辞書を引く回数が各段に減ります。動詞は、現在幹、完了幹、目的分詞幹を覚えてしまいましょう。
各自勉強スタイルがあると思いますが、ここでは私が勉強する際に気をつけていたことを紹介します。それは、quamとutの解釈です。
quam
・比較の対象を示す(英語のthanにあたるもの)
・関係代名詞(女性単数対格)
・疑問詞「どれほど、どの程度」
quamが出てきたら、どれにあたるのかを確認しましょう。utに出くわしたときも、文法書や辞書を見つつ、どの用法なのかを見極めましょう。
ut
・~のように
・~のとき
・~するために
時間を見つけて、『古典ラテン語文典』を手に取るのもよいかと思います。
また、独学の方は機会があれば講習会などに参加して、ラテン語に取り組んでいる方と対面してみましょう。刺激になっていい影響があること必至です。
上級編:暗唱する
ここでの上級とは、一語ずつ辞書を引かずとも、とりあえずラテン語を自分なりに目的をもって読めている段階のこととします。
上級編の方がこの記事を読んでいるかはさだかではありませんし、この場で上級者に向けて何を語るかは迷うところでありますが、自分がふだん気をつけていることを書いてみますので、必要に応じて参考にしてみてください。
・習慣を保つ
ここまできた人はすでにラテン語学習の習慣がついているでしょう。その習慣を保つため、また少し負荷をかけるために、暗唱などいかがでしょうか?
中級で紹介した音読の強化版です。音読にとどまらず、丸暗記を試みるのです。一度覚えてしまえば、見えるものも変わってきて、処理速度もしだいに上がってくるでしょう。筆記用具や辞書がなくてもできるのもよいところです。
語学力に効くだけでなく、電車の中や、スマホが手元にないとき、家事をしている最中などに暗唱したものを思い出すと暇つぶしにもなります。
・「古文常識」にあたるもの
高校の古典で「古文常識」というものを勉強したかと思います。ラテン語で古代のものを読む際にも、そのテキストの前提知識や背景を知ることから始めるのがおすすめです。文法的には解釈ができても、いまいち読み取れない場合は、書かれた時代の風習や習慣などに立ち返ってみましょう。
・そもそもテキストが不正確
古代や中世に書かれたラテン語は、長らく手書きで伝承されてきたため、テキストそのものが筆者本人の書いたものの通りとは限りません。読んでいるテキスト内の一部の語が、現代の校訂者によって複数の選択肢の中から採用されたものであることは認識しておきましょう。
あとは量をこなすことでしょうか。
私自身は、先に紹介した音読と暗唱を心がけています。教わった何人かの先生が実践されていて熱心にすすめられたのがきっかけです。勉強に気が乗らないときでも、とりあえず手元の文章を音読したり、覚えているものを暗唱してみます。そうすると、ここの単語はどういう意味だったか、この文法事項ってあれだったっけと気になり、辞書やら文法書を手に取ることになったりします。
また、ある程度の分量を暗唱するには、意味を把握している必要があります。暗唱を目的とするだけで、気づいたらあれこれ調べることになってしまうのはなんともありがたいです。
『上達の法則』という本には、上級者になる特訓法として「大量の暗記暗唱」をしてみることや「反復練習」をすることの他に、「独自の訓練方法を考える」ことも紹介されています。
試行錯誤しながら、それぞれの目的に応じた勉強を続けていきましょう。私もその最中です。
参考文献
まとめ
自らの経験をふまえて、あの時ああしとけばよかったななどと、かつての自分にアドバイスするように書いてみました。振り返ってみます。
全般編:英語学習とは真逆と心得る
時間のかかる覚悟をし、わからなくても先に進む。忘れてもOK
初級編:つづけること、習慣づくりが大事。まず全体像を把握
中級編:音読し、ストックを増やす
上級編:暗唱をする
ラテン語を続けていく参考になればうれしいです。






